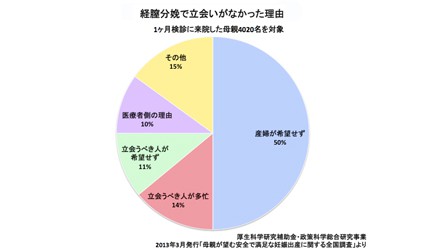ふたつめが、<出産育児一時金>。企業の健康保険や国民健康保険など、すべての健康保険加入者が出産の際、1子につき42万円(*2)が支給される制度です。これまでこの一時金は、出産にかかった費用を自己負担で支払った後に、健康保険から後日支給されてきました。しかし、最近では一時金の請求と受け取りを医療機関などが直接行う「直接支払制度」の改善によって、退院時に窓口で支払うのは出産費用と一時金の差額のみで、一括で全額を支払わなくて済むようになりつつあります。
以上の2つは、多くのママたちに認知、活用されていますが、次に挙げるような、妊娠、出産に間接的に関係する公的支援は意外と見落とされがちな面があるようです。
まず、医療機関や薬局で支払った金額が一定額を超えた場合に、超えた分の金額を支給してくれる<高額療養費制度>。それから、健診費や産院への交通費を含めて年間の医療費が10万円を超えた場合に適用される<医療費控除>があります。これらを利用するために、家族全員分の医療費の領収書、産院への交通費、薬局などで購入した薬のレシートは必ずとっておくように習慣づけましょう。
- *2:在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円となる。
働くママにはその他の支援も
このように、さまざまな公的支援を上手に利用すれば、妊娠、出産にかかる自己負担額は想像よりも“安く済む”というのが実態のようです。さらに、働くママたちには、産前産後の生活をサポートするために次のような給付金制度が設けられています。
まずは、<出産手当金>。勤め先の健康保険から支払われる制度で、標準報酬月額を30で割った日当にあたる金額の3分の2が、産前の6週間、産後の8週間の計98日分支払われます。
次に、<育児休業給付金>。雇用保険から支払われる1歳未満(*3)の子どもを養育するために育児休業を取得した際に適用される制度で、その養育の間1ヶ月あたり、休業開始時の賃金の月額(*4)の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%・*5)が支給されます。
「1年以上同じ雇用主のもとでの勤務」などが条件となりますが、たとえば月給18万円の女性が産休、育休を取得した場合、合計170万円近くの金額が支給されるという試算になります。このように意外と充実している公的支援ですが、働くママ向けの制度はもちろん、今までみてきた制度はいずれも、利用するためには自分からの申請が必要になります。
できれば比較的時間に余裕のある出産前に、自分はどんな公的支援の対象になるかを認識して、申請に必要な条件、書類、申請期間、窓口を職場や公的機関に聞いておきましょう。そうやって自主的に調べ行動することで、受給漏れがないようしっかり準備をしていきたいものですね。
- *3:パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月未満、保育所への入所申込みをしたが、その子が1歳に達する日後の期間について当面その実施がおこなわれなかった場合は1歳6ヶ月未満。
- *4:「休業開始時賃金日額×支給日数」を指す。
- *5:平成26年4月1日以降に育休を取得する場合。それ以前に取得している場合は50%。