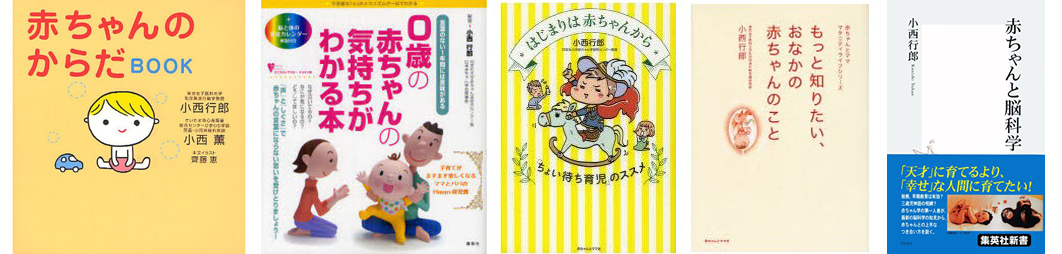第一部では、赤ちゃんの眠りのメカニズムについて、第二部では、現代の赤ちゃんを取り巻く環境から赤ちゃんや子どもの睡眠を学んできました。シリーズ最終回となる第三部では、赤ちゃんの生活リズムの確立方法について、同志社大学赤ちゃん学センター長の小西先生に教えていただきました。
赤ちゃんの生活リズムを確立するためにできること
たとえ夜中であろうともお構いなしに起きては泣きじゃくる生まれたばかりの赤ちゃん。新米ママやパパは「なんで、こんな時間に泣いちゃうの?」と思われるかもしれませんが、長年医師として赤ちゃんを見守ってきた小西先生によると、生まれたばかりの赤ちゃんは、時間の感覚が「ママと8時間ぐらいずれているように感じる」とのこと。だから時間など関係なく泣いちゃうのかもしれません。たしかに真っ暗なおなかの中で、10か月間も自由に寝たり起きたりを繰り返してきたのですから、昼夜逆転していても不思議ではありませんね。
そんな赤ちゃんは、出産によって突然世の中を体験することになります。ママのお腹から出てきたばかりの赤ちゃんは、今までと違う明るくて広い空間に戸惑いながらも、必死に環境に順応していこうとします。
そんな中で、親として赤ちゃんに最初に教えるべきことのひとつは正しい生活のリズムだと小西先生は指摘します。
「最初の数か月はちょこちょこ起きて泣きますが、その間にも、ママ・パパは規則正しい生活のリズムを教えてほしいと思います。つまり、朝の光を浴びて起きること、暗くなったら眠ることを意識して赤ちゃんと生活をしてほしいのです。もちろん、赤ちゃんに生活リズムをすり込むためには、お腹の中に赤ちゃんがいる時から、ママが一定のリズムで生活することも大切です。また生活のリズムを整えるためにも、また体内で(睡眠との関係も深い栄養素である)ビタミンDを生成するためにも、日光をしっかり浴びてほしいと思います。それは妊婦のため、ひいては赤ちゃんの成長にもよい影響があると考えています」(小西先生)
良質な睡眠との関連性が高いとされるビタミンDは、食べ物からも摂取できます。特に母乳育児をされているママは、鮭や卵などビタミンDが豊富に含まれる食品を意識してとる必要があるかもしれませんね。
また、よく眠る赤ちゃんのためには、夜眠るときに部屋を暗くするということも大切。
「これはよく言われることではあるのですが、海外に比べて(現代の)日本の照明はすごく明るい。それが、赤ちゃんが体のリズムを作っていく上での障害になっている一つの要因だと考えられます。7時でも8時でもこうこうと明かりがついている部屋にいては、赤ちゃんも眠くなりづらいので、夜になったら部屋の明かりをなるべく暗くして、赤ちゃんが眠る準備を整えてあげてください」(小西先生)
赤ちゃんを寝せる時、暗闇を怖がるのではないかと考えて、小さな照明をつけてしまいがちですが、こうした気遣いは逆効果になってしまうとのこと。これは注意したいですね。
最近はタブレットやスマホで動画などを楽しむ赤ちゃんも増えてきています。それについて小西先生は「寝る前、少なくとも3時間前には見せないようにしてください。スマホやタブレットが発するブルーライトを浴びるとメラトニンの生成が抑えられ、熟睡できなくなってしまいます。タブレットやスマホを見るのは、夕方の5時までという事にしてもらいたいです」というアドバイスをしてくださいました。
今までのやり方を変えるのは、ちょっと大変そうな気もしますが、夜ぐっすり眠る赤ちゃんは、ママとパパにも安らかな眠りの時間をプレゼントしてくれますよ。そして、家族みんなで元気に目覚める朝は、楽しい一日に続いていくはずです。
最後に小西先生から、こんなお言葉をいただきました。
「第2部でも説明しましたが、よく眠る赤ちゃんに育てるためには、ママとパパが自分たちの生活時間を見直し、赤ちゃんのリズムに合わせた暮らし方を心がける必要があります。もちろん、働き方もさまざまで全てのママやパパが、赤ちゃんのリズムにあわせた生活をすることは現実的ではないかもしれない。ただ、そのために赤ちゃんの睡眠、さらには赤ちゃんの成長や未来が犠牲になっていることも忘れてはいけません。そして、その問題をすべてママやパパが抱え込んではいけない。社会全体で“赤ちゃんの睡眠不足問題”について真剣に取り組む必要があります。ずっと赤ちゃんを見続けてきた私は、この問題の深刻さをみなさんに知っていただきたいと思っています」(小西先生)
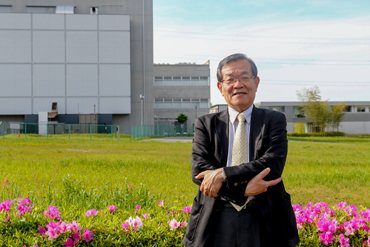
小西先生プロフィール
日本赤ちゃん学会理事長
同志社大学赤ちゃん学研究センター
センター長/教授
兵庫県立リハビリテーション中央病院・子どもの睡眠と発達医療センター
小児科医(小児神経専門医)
京都大学医学部卒業。同大学附属病院未熟児センター、福井医科大学勤務を経て、1989年に文部省在外研究員としてオランダにて発達行動学を学ぶ。帰国後は、埼玉医科大学小児科の教授を務めた後、2001年に東京女子医科大学に乳児行動発達学講座を開設し、教授となる。また、同年に赤ちゃんをまるごと考える“日本赤ちゃん学会”を設立。
2008年、同志社大学大学院心理学科の教授、同大学赤ちゃん学研究センター長に就任。
2013年、兵庫県立リハビリテーション中央病院・子どもの睡眠と発達医療センター長に就任(2013年4月~2017年3月)。
主な著書は、『赤ちゃんと脳科学』(集英社新書)、『早期教育と脳』(光文社新書)、『もっと知りたい、おなかの赤ちゃんのこと』(赤ちゃんとママ社)、『赤ちゃんのからだBOOK』(海竜社)、『赤ちゃんのしぐさで気持ちがわかる本』(PHP研究所)、『0歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本』(講談社)など